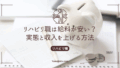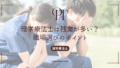作業療法士は「転職が多い職種」として話題に上ることがよくあります。これから作業療法士を目指す学生さんにとっては、将来のキャリアへの不安要素として気になるポイントでしょう。現役の作業療法士の方も、同僚や先輩が次々と転職していく姿を見て「なぜこんなに転職が多いのだろう」と疑問に思っているかもしれません。
確かに作業療法士は他の職種と比較して転職率が高い傾向にありますが、それは必ずしもネガティブな理由だけではありません。むしろ、作業療法士という専門職ならではの特性や、キャリアアップへの積極的な姿勢が背景にあることも多いのです。
本記事では、統計データを踏まえながら作業療法士の転職が多い理由を整理し、転職を前向きなキャリア形成の一環として捉える視点をご紹介します。これから作業療法士を目指す方も、現在転職を検討中の方も、今後のキャリアを考えるヒントとしてお役立てください。
作業療法士は転職が多いって本当?
「作業療法士は転職が多い」という話をよく耳にしますが、実際のところはどうなのでしょうか。統計データを基に客観的に検証し、理学療法士や看護師といった他の医療職との比較も行いながら、転職の多さが持つ意味について考えてみましょう。
統計やデータから見るOTの離職率転職率
作業療法士の転職が多いという話は、単なる噂ではなく実際のデータでも裏付けられています。日本作業療法士協会の統計調査によると、作業療法士の離職率は年間約10~15%程度で推移しており、これは一般的な職種と比較して高い水準にあります。
特に新卒で就職した作業療法士の場合、3年以内に転職する割合が約30~40%に達するという調査結果もあります。この数字だけを見ると確かに高く感じられますが、背景には作業療法士という職種特有の事情が存在しています。
また、転職回数についても注目すべき点があります。作業療法士のキャリアの中で、1回も転職をしないという人は実は少数派で、多くの作業療法士が2~3回の転職を経験しています。中には5回以上転職している方もおり、これは他の医療従事者と比較しても顕著な特徴といえるでしょう。
理学療法士や看護師との比較
同じリハビリテーション専門職である理学療法士と比較すると、作業療法士の方がやや転職率が高い傾向にあります。理学療法士の離職率が年間約8~12%程度であるのに対し、作業療法士は前述の通り10~15%となっています。
この差の背景には、作業療法士の方が多様な分野での活躍が期待されていることが関係しています。身体機能への介入が中心となる理学療法士と比較して、作業療法士は精神科、小児科、認知症ケア、就労支援など、より幅広い領域でのニーズがあります。そのため、キャリアの過程でさまざまな分野を経験したいという動機から転職を選択する作業療法士が多いのです。
看護師との比較では、看護師の離職率は約11%程度とされており、作業療法士とほぼ同水準です。しかし、看護師の場合は夜勤や激務による身体的負担が転職理由の上位を占めるのに対し、作業療法士の転職理由はより多様化している点が特徴的です。
「転職が多い=ネガティブ」とは限らない理由
転職が多いことを単純にネガティブに捉える必要はありません。作業療法士の場合、転職が多い理由の多くは前向きなキャリア形成に関連しているからです。
まず、作業療法士の職場は病院、クリニック、介護施設、訪問リハビリ、就労支援施設、行政機関など非常に多岐にわたります。それぞれの職場で求められるスキルや知識が異なるため、幅広い経験を積むためには必然的に転職を重ねることになります。
また、作業療法士は「その人らしい生活」を支援する専門職であるため、自分自身のライフステージの変化に合わせて働き方を調整したいという意識が強い傾向にあります。結婚、出産、育児、介護などのライフイベントに応じて、より働きやすい環境を求めて転職することは、決して逃げや妥協ではなく、自分らしいキャリアを築くための積極的な選択なのです。
さらに、作業療法士は比較的転職市場での需要が安定しているため、転職に対する心理的ハードルが低いという側面もあります。これは専門職としての強みであり、自分のキャリアを主体的にコントロールできる証拠でもあります。
作業療法士が転職を多くする理由
では、なぜ作業療法士は転職を選択することが多いのでしょうか。その背景には、職業特有の様々な事情があります。給与面での課題から、専門性を追求したいキャリア志向、さらにはライフステージの変化に応じた働き方の調整まで、具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
給料や待遇に不満がある
作業療法士の転職理由として最も多く挙げられるのが、給料や待遇に関する不満です。作業療法士の平均年収は約350~450万円程度とされていますが、勤続年数が長くなっても大幅な昇給が期待しにくい職場が多いのが現実です。
特に医療機関では、診療報酬制度の影響により、リハビリテーション部門の収益性に限界があります。そのため、作業療法士の給与体系も頭打ちになりやすく、10年、20年と勤務を続けても年収が400万円台から大きく変わらないというケースも少なくありません。
また、昇進のポストが限られていることも給与上昇の阻害要因となっています。主任や係長といった管理職のポジションは各部署に数名程度しかなく、年功序列での昇進を待っていても、なかなか昇格の機会が訪れません。そのため、管理職としてのキャリアを築きたい作業療法士は、より条件の良い職場や昇進の可能性がある職場への転職を選択することになります。
さらに、同じ作業療法士でも職場によって給与水準に大きな差があることも、転職を促進する要因となっています。公立病院や大学病院では比較的安定した給与が期待できる一方、民間のクリニックや介護施設では経営状況によって待遇に大きなばらつきがあります。このような情報格差が明らかになったとき、より良い条件を求めて転職を検討する作業療法士が増えるのです。
人間関係や職場環境の問題
作業療法士の職場は比較的小規模なところが多く、人間関係の問題が転職理由となることも珍しくありません。リハビリテーション科の作業療法士は、多くの職場で5~10名程度の小さなチームで構成されており、一度人間関係にトラブルが生じると、その影響を避けることが困難になります。
小規模な職場では、一人の作業療法士の影響力が大きく、上司や先輩との相性が悪い場合、日々の業務に大きなストレスを感じることになります。また、チーム内での価値観や治療方針の違いが表面化したとき、調整役となる中間管理職が不在だったり、機能していなかったりする場合があります。
さらに、作業療法士の職場では、専門性の高さゆえに外部からの理解が得られにくいという問題もあります。特に介護施設や在宅サービスなどで働く場合、他職種のスタッフから作業療法の専門性が十分に理解されず、適切な連携が取れないことがあります。このような環境では、専門職としてのやりがいを感じにくく、より理解のある職場を求めて転職を考える作業療法士が多くなります。
職場環境の問題としては、設備や機器の不足も重要な要因です。作業療法には多様な道具や環境が必要ですが、予算の制約により十分な設備が整っていない職場も存在します。このような環境では、質の高い作業療法を提供することが困難になり、専門職としての成長や満足感を得ることができません。
専門性を活かしたいキャリア志向
作業療法士の大きな特徴の一つは、その専門性の多様性です。身体障害、精神障害、発達障害、認知症など、対象となる疾患や障害の種類が幅広く、それぞれの分野で求められる知識やスキルが大きく異なります。このような専門性の多様性が、キャリア志向の高い作業療法士の転職を促進する要因となっています。
例えば、急性期病院で身体障害のリハビリテーションを経験した作業療法士が、次は精神科病院や精神科デイケアで精神障害者への支援に挑戦したいと考えることはよくあります。また、成人の患者さんとの関わりを通じて小児分野への興味を抱き、小児専門病院や療育センターへの転職を希望する作業療法士も少なくありません。
訪問リハビリテーションも、近年注目されている分野の一つです。病院での治療とは異なり、利用者の自宅や生活環境で直接支援を行う訪問リハビリは、より生活に密着した作業療法を実践できる場として人気が高まっています。このような新しい分野への挑戦を通じて、専門性を深めたいと考える作業療法士が転職を選択するケースが増えています。
さらに、就労支援や地域包括ケア、介護予防など、作業療法士の活躍の場は年々拡大しています。これらの新しい分野では、従来の医療モデルとは異なるアプローチが求められるため、キャリアアップを目指す作業療法士にとって魅力的な転職先となっています。このような専門性の追求は、作業療法士としてのスキルアップにつながる前向きな転職理由といえるでしょう。
ライフイベントとの両立
作業療法士の約7割を女性が占めていることから、結婚、出産、育児といったライフイベントが転職の大きな要因となっています。これらのライフステージの変化に合わせて、働き方を調整できる職場を求めて転職する作業療法士は非常に多いのが現状です。
妊娠・出産期においては、夜間勤務のない職場や、妊娠中の身体的負担を考慮してくれる職場への転職を希望する作業療法士が増えます。特に急性期病院などで働いていた場合、緊急対応や長時間勤務が求められることがあるため、より安定した勤務環境を提供する回復期病院や外来クリニックへの転職を選択することが多くなります。
育児期に入ると、勤務時間の調整がしやすい職場への転職がさらに重要になります。短時間勤務制度が充実している職場、託児所が併設されている病院、在宅勤務が可能な職種(例:書類作成業務や研修講師など)への転職を検討する作業療法士が多く見られます。
また、子どもの成長に合わせて勤務地を変更する必要が生じることもあります。配偶者の転勤に伴う引越し、子どもの進学に合わせた居住地の変更などにより、新しい地域での転職を余儀なくされる作業療法士も少なくありません。
介護期においても同様の傾向が見られます。両親や配偶者の介護が必要になった際、勤務時間の融通が利く職場や、在宅ワークが可能な職種への転職を選択する作業療法士が増えています。このような転職は、ライフワークバランスを保ちながら専門職としてのキャリアを継続するための現実的な選択といえるでしょう。
職場ごとの特色が大きいため自分に合う環境を探す傾向
作業療法士の職場は、その種類や規模、運営方針によって働く環境が大きく異なります。同じ「病院」という分類であっても、急性期病院、回復期病院、慢性期病院では求められる役割や働き方が全く違います。また、医療法人、社会福祉法人、株式会社など、運営母体の違いによっても職場文化や待遇に大きな差があります。
このような職場ごとの特色の違いが、作業療法士の転職を促進する要因となっています。最初に就職した職場で「こんなはずではなかった」と感じる新人作業療法士は多く、自分の価値観や働き方に合った職場を見つけるまで、複数回の転職を経験することも珍しくありません。
例えば、チーム医療を重視する病院で働いていた作業療法士が、より個別性を重視した治療を行いたいと考えて個人クリニックに転職するケースがあります。逆に、個人の裁量が大きすぎる職場で不安を感じ、より組織的なサポート体制が整った大規模病院への転職を希望する場合もあります。
勤務時間についても、職場によって大きな違いがあります。残業が常態化している職場もあれば、定時での帰宅が徹底されている職場もあります。研修や勉強会の頻度、学会参加への支援体制、資格取得へのサポートなども職場によって様々です。
さらに、治療方針や理念の違いも重要な要因です。医学モデルを重視する職場もあれば、生活モデルを中心とした支援を行う職場もあります。エビデンスベースの治療を重視する職場もあれば、経験や直感を大切にする職場もあります。このような価値観の違いは、作業療法士の職業満足度に大きな影響を与えるため、自分に合った環境を求めて転職を繰り返すことになるのです。
転職が多いことは悪いことではない
ここまで作業療法士の転職が多い理由について説明してきましたが、転職の多さを単純にネガティブに捉える必要はありません。むしろ、専門職としての成長や理想的な働き方の実現に向けた前向きなステップとして捉えることができます。転職によって得られるメリットについて考えてみましょう。
経験を積むことでスキルが広がる
作業療法士にとって転職の多さは、むしろスキル向上の大きなチャンスと捉えることができます。異なる職場での経験を積むことで、多様な疾患や障害への対応能力が身につき、専門職としての幅が大きく広がります。
急性期病院では素早い評価と治療計画の立案スキルが身につき、回復期病院では継続的な治療とチームアプローチの重要性を学べます。介護施設では生活の質の向上に焦点を当てたアプローチを、精神科では心理社会的な側面への配慮を深く理解できるようになります。
このように、職場を変えることで得られる経験の多様性は、一つの職場に長く勤務していては決して得ることのできない貴重な財産となります。特に作業療法士の場合、対象となる疾患や障害の種類が幅広いため、多様な経験を積むことで、より適切で効果的な治療を提供できるようになります。
また、異なる職場での経験は、問題解決能力の向上にも寄与します。職場ごとに異なる制約や環境の中で最適な治療を提供するためには、柔軟な思考と創造性が必要になります。このような能力は、転職を通じて様々な状況に対応した経験があるからこそ培われるものです。
さらに、多様な経験を持つ作業療法士は、後輩指導や教育の場面でも重要な役割を果たします。実際の臨床現場での豊富な経験談は、新人作業療法士にとって非常に価値のある学びとなります。このように、転職による経験の蓄積は、個人のスキルアップだけでなく、職業全体の発展にも貢献する重要な要素となっています。
キャリアアップや専門性獲得につながる
転職は作業療法士にとって、キャリアアップや専門性獲得の重要な手段でもあります。一つの職場に留まっていては得られない管理職経験や、特定分野での深い専門性を獲得するためには、戦略的な転職が効果的な場合があります。
例えば、認定作業療法士や専門作業療法士の資格取得を目指す場合、特定の分野での豊富な臨床経験が必要になります。このような専門資格を取得するためには、該当する分野での集中的な経験を積める職場への転職が有効です。手の外科専門病院での経験、精神科専門病院での長期勤務、小児専門施設での実践など、専門性を深めるための環境を求めて転職することは、キャリア形成の重要な戦略といえます。
管理職を目指す場合も、転職が有効な手段となることがあります。現在の職場で管理職のポストが空かない場合、他の職場でのマネジメント経験を積むことで、将来的により高いポジションを目指すことができます。また、異なる職場での管理経験は、多様な組織運営の手法を学ぶ機会ともなり、より優れたリーダーシップ能力の獲得につながります。
研究や教育分野でのキャリアを目指す場合も、転職が重要な役割を果たします。大学院での研究活動と臨床実践を両立できる職場、教育機関での教員ポジション、研究活動を推進する医療機関など、自分の目指すキャリアに適した環境を求めて転職することは、専門職としての成長にとって非常に有効です。
自分に合った職場に出会いやすくなる
転職経験を重ねることで、自分にとって理想的な職場環境や働き方が明確になってきます。最初の就職では、実際の職場環境や業務内容について十分に理解しないまま就職先を決めることが多いため、入職後にギャップを感じることも少なくありません。しかし、複数の職場を経験することで、自分の価値観や働き方の preferences が明確になり、より自分に合った職場を見つけやすくなります。
職場の規模についても、小規模でアットホームな環境を好む作業療法士もいれば、大規模で組織的なサポートが充実した環境を求める作業療法士もいます。治療方針についても、医学モデル重視か生活モデル重視か、個別治療中心かグループ治療中心かなど、様々な選択肢があります。このような preferences は、実際に異なる環境で働いてみなければわからないことが多いのです。
また、転職を通じて様々な職場を知ることで、業界全体の動向や将来性についても理解が深まります。成長性のある分野、将来性に不安のある分野、自分のライフステージに適した働き方など、長期的な視点でのキャリア設計が可能になります。
さらに、転職活動を通じて築かれる人的ネットワークも重要な財産となります。転職エージェントとの関係、面接で出会った他の作業療法士との交流、新しい職場での人間関係など、これらのネットワークは将来のキャリア形成にとって貴重な資源となります。このようなネットワークを通じて、さらに良い転職機会や情報を得ることができるようになるのです。
転職を考えるときに大切なポイント
転職がキャリア形成に有効だと理解できても、実際に転職を成功させるためには戦略的なアプローチが必要です。漠然とした不満だけで転職活動を始めても、同じような問題を繰り返してしまう可能性があります。ここでは、転職を成功に導くための具体的なポイントをお伝えします。
転職の目的を明確にする
転職を成功させるためには、まず転職する目的を明確にすることが最も重要です。「なんとなく今の職場に不満がある」「周りの人も転職しているから」といった曖昧な理由では、転職先でも同様の問題に直面する可能性が高くなります。
給与面での改善を求める場合は、具体的な金額や条件を明確にしましょう。年収をいくら上げたいのか、昇進の可能性はどの程度重視するのか、賞与や各種手当の重要度はどの程度なのかを整理することが大切です。また、給与だけでなく、福利厚生や退職金制度なども含めた総合的な待遇改善を考慮することが重要です。
働きやすさを重視する場合は、具体的にどのような働き方を実現したいのかを明確にします。勤務時間の柔軟性、有給取得のしやすさ、残業時間の少なさ、職場の人間関係など、優先順位をつけて整理しましょう。特にライフイベントとの両立を考えている場合は、育児休暇制度、短時間勤務制度、託児所の有無なども重要な検討項目となります。
専門性の向上を目的とする場合は、どの分野でのスキルアップを目指すのか、将来的にどのような専門職になりたいのかを明確にします。認定作業療法士や専門作業療法士の取得を目指すのか、管理職としてのキャリアを積みたいのか、研究や教育分野での活動を希望するのかによって、選ぶべき転職先が大きく変わってきます。
職場見学や口コミを活用する
転職先を決定する前に、必ず職場見学を行うことが重要です。求人票やホームページの情報だけでは、実際の職場環境や雰囲気を十分に把握することはできません。職場見学を通じて、実際に働いている作業療法士の様子、施設の設備状況、患者さんや利用者との関わり方などを直接確認することができます。
職場見学では、リハビリテーション室の設備や機器の充実度、作業療法士の配置状況、他職種との連携の様子などを注意深く観察しましょう。また、可能であれば実際の治療場面を見学させてもらい、その職場での作業療法の特徴や方針を理解することが大切です。
職場見学の際は、遠慮せずに質問することも重要です。残業時間、有給取得率、研修制度、昇進の可能性、職場の課題や今後の方針など、気になる点は積極的に確認しましょう。また、可能であれば複数の職員と話をする機会を設けてもらい、様々な角度から職場の情報を収集することが効果的です。
口コミサイトや SNS での情報収集も有効な手段です。転職会議、OpenWork、Indeed などの口コミサイトでは、実際にその職場で働いた経験のある人の生の声を知ることができます。ただし、口コミ情報は個人的な主観が強く反映されている場合があるため、複数の情報源から情報を収集し、客観的に判断することが重要です。
また、同じ作業療法士のネットワークを活用することも効果的です。学会や研修会で知り合った作業療法士、養成校の同期や先輩後輩、現在の職場の同僚などから、転職先の職場について情報を収集することができる場合があります。このような人的ネットワークを通じた情報は信頼性が高く、貴重な情報源となることが多いです。
転職サービスやエージェントを上手に利用する
作業療法士の転職において、専門の転職サービスやエージェントを活用することは非常に有効です。リハビリ職専門の転職サービスでは、一般的な転職サイトでは見つからない求人情報や、業界に特化した詳細な情報を得ることができます。
転職エージェントの最大のメリットは、キャリアカウンセリングを通じて自分の強みや適性を客観的に把握できることです。これまでの経験やスキル、転職の目的などを整理し、それに基づいて最適な求人を紹介してもらえます。また、自分では気づかなかった新しいキャリアの可能性についても提案してもらえる場合があります。
履歴書や職務経歴書の作成についても、プロのサポートを受けることができます。作業療法士としての経験や実績を効果的にアピールする方法、志望動機の書き方、面接での質問対策など、転職活動の各段階で具体的なアドバイスを受けることができます。
給与交渉や勤務条件の調整についても、転職エージェントが代行してくれる場合があります。自分では言いにくい条件面の交渉を、プロが代わりに行ってくれるため、より良い条件での転職が実現しやすくなります。
ただし、転職エージェントを利用する際は、複数のサービスを比較検討することが重要です。エージェントによって得意分野や保有している求人の傾向が異なるため、自分の希望に合ったサービスを選択することが大切です。また、エージェントとの相性も重要な要素ですので、信頼できるキャリアアドバイザーと出会えるまで、必要に応じて複数のサービスを試してみることをお勧めします。
まとめ
作業療法士の転職が多いことは確かな事実ですが、それは決してネガティブなことばかりではありません。むしろ、専門職としての成長や、自分らしいキャリアの実現のための前向きな選択である場合が多いのです。
給与や待遇の向上、専門性の追求、ライフイベントとの両立、自分に合った職場環境の探求など、作業療法士が転職を選択する理由は多様です。これらの理由の多くは、より良い作業療法士になりたい、より充実した職業人生を送りたいという前向きな動機に基づいています。