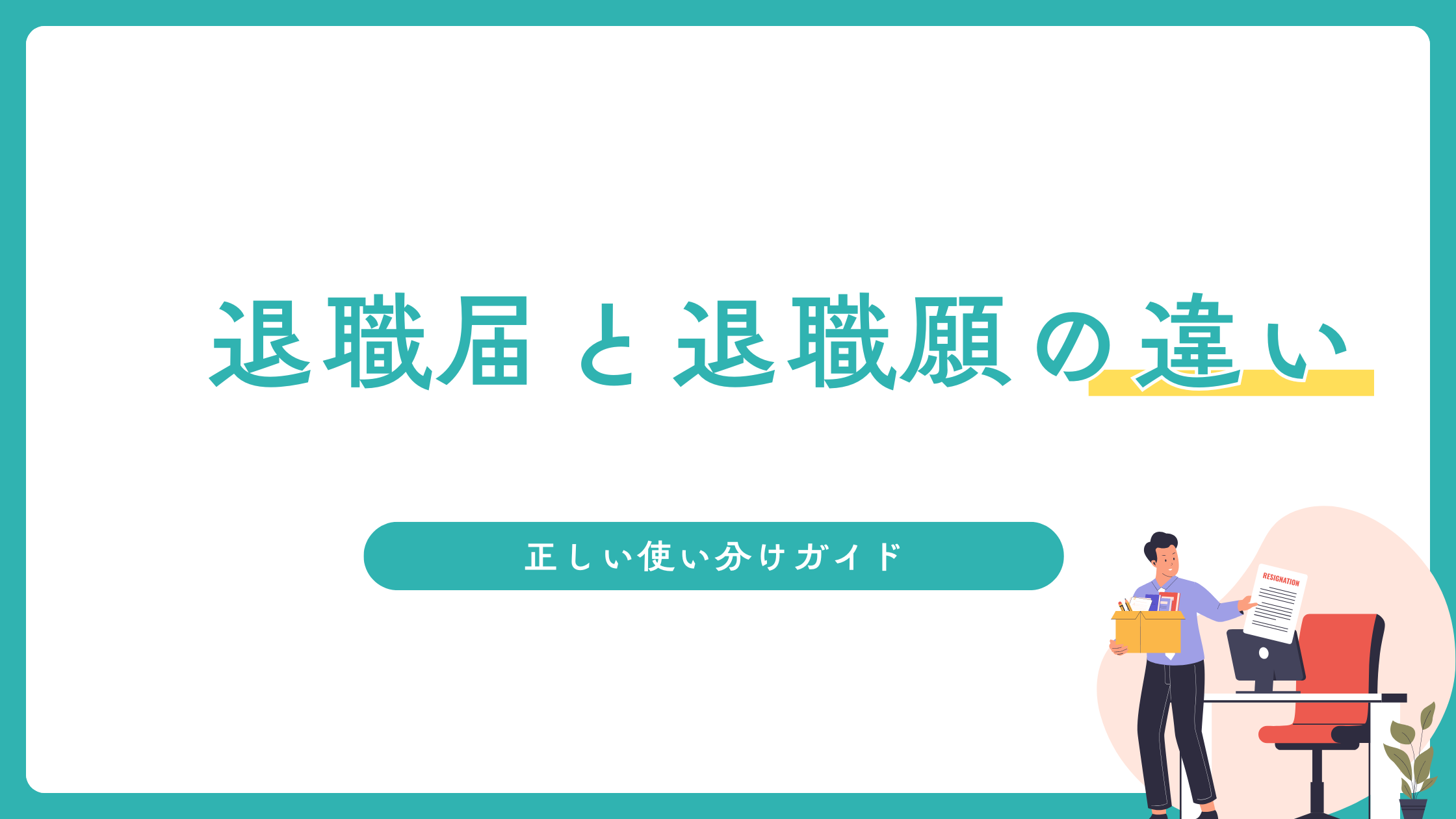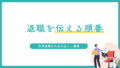退職を考えているとき、「退職届と退職願ってどう違うの?」と疑問に思う方は少なくありません。実際、この2つの書類は似ているようで、法的効力や提出する場面が大きく異なります。間違った書類を提出してしまうと、後々トラブルになったり、円満退職の妨げになったりすることもあるため、正しい知識を身につけることが重要です。
本記事では、退職届と退職願の基本的な違いから、どちらを提出すべきか、正しい書き方、提出時の注意点まで、退職に関わる書類について包括的に解説します。これから退職を検討している方、すでに退職の意思を固めている方も、ぜひ参考にしてトラブルのない円滑な退職手続きを進めてください。
退職届と退職願の基本的な違い
退職届と退職願は、どちらも退職に関わる書類ですが、その性質や法的効力には明確な違いがあります。まずは、この2つの基本的な違いを理解しましょう。
退職願→願い出の段階
退職願は、その名前の通り「退職したい」という意思を会社に対して「願い出る」文書です。つまり、退職に関する相談や交渉の出発点となる書類であり、まだ退職が確定していない段階で提出するものです。
退職願の特徴として、会社側に退職を「お願いする」という性質があります。そのため、文面も「〜させていただきたく」「〜願い出ます」といった敬語を使った表現になります。この段階では、まだ会社との話し合いの余地があり、場合によっては退職時期の調整や、退職理由についての相談も可能です。
また、退職願は一般的に撤回が可能とされています。提出後に気持ちが変わったり、会社から慰留があったりした場合、まだ会社が承認していなければ取り下げることができる場合が多いです。ただし、会社が承認した後は撤回が困難になるため、提出前によく検討することが大切です。
退職届→意思表示の確定
一方、退職届は退職が決まった後に提出する正式な文書です。会社との話し合いが終わり、退職日や引き継ぎ事項などが確定した段階で提出します。退職届は「届け出る」という性質があり、退職の意思が確定していることを示す書類です。
退職届の文面は、退職願とは異なり「〜いたします」「〜届け出ます」といった断定的な表現を使います。これは、もはや相談や交渉の段階ではなく、確定した事実を報告するという意味合いがあるためです。
退職届は、労働契約の解約を正式に通知する書類としての役割も持っています。そのため、提出することで労働者の退職に関する法的な手続きが開始されることになります。会社側も、退職届を受理することで、退職に関する各種手続きを進めることになります。
法的効力の違い
退職願と退職届の最も重要な違いの一つが、法的効力の違いです。この違いを理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
退職願は、前述の通り「お願い」の段階であるため、会社が承認するまでは撤回が可能です。ただし、会社が承認した場合は、労働契約の合意解約が成立したとみなされ、その後の撤回は困難になります。
一方、退職届は提出した時点で労働者の退職意思が確定したものとみなされます。そのため、一度提出すると撤回は原則として困難です。民法では、労働者が退職の意思を表示した場合、2週間後に労働契約が終了すると定められており、退職届はこの意思表示にあたります。
つまり、退職届を提出すると、会社の同意がなくても法的には退職が可能になりますが、同時に撤回も困難になるという特徴があります。そのため、退職の意思が完全に固まってから提出することが重要です。
どちらを提出すべき?
退職届と退職願のどちらを提出すべきかは、退職の状況や会社の方針によって異なります。一般的な流れと判断基準について詳しく見ていきましょう。
まずは退職願で意思を伝えるのが一般的
多くの場合、退職の手続きは退職願から始まります。これは、円満退職を目指す上で最も適切なアプローチと考えられているためです。
退職願を先に提出することで、会社との話し合いの機会を設けることができます。退職時期の調整、業務の引き継ぎ計画、退職理由の説明など、様々な点について相談することが可能です。特に、重要なプロジェクトに関わっている場合や、後任者の育成が必要な場合は、会社側と十分に調整する時間を確保することが重要です。
また、退職願から始めることで、会社側に対して「相談をしたい」「円満に退職したい」という姿勢を示すことができます。これは、退職後の人間関係を良好に保つ上でも重要な要素です。転職先で元の職場との関係が必要になったり、将来的に再び関わりを持ったりする可能性を考えると、円満退職は大きなメリットとなります。
さらに、退職願は撤回が可能であるため、万が一気持ちに変化があった場合や、会社から魅力的な慰留提案があった場合に対応する余地を残すことができます。
会社から指示があれば退職届を出す
退職願を提出し、会社との話し合いが進んで退職が承認された後は、通常、会社から退職届の提出を求められます。この段階では、会社の指示に従って退職届を作成・提出するのが一般的です。
会社によっては、退職願の承認と同時に退職届の提出を求める場合もあります。また、退職に関する具体的な日程や条件が確定した段階で、正式な記録として退職届を求めるケースもあります。
重要なのは、会社の指示を適切に理解し、求められた書類を正確に作成することです。退職届を求められた場合は、退職日や退職理由などの詳細が確定していることを前提として、正確な情報を記載して提出しましょう。
なお、会社によっては独自のフォーマットや手続きを定めている場合があります。そのため、退職届の提出を求められた際は、書式や提出方法についても確認することが大切です。
企業によって必要書類が異なる
退職手続きに関する詳細は、企業によって大きく異なります。そのため、退職を検討する際は、まず自社の就業規則を確認することが重要です。
就業規則には、退職手続きに関する具体的な規定が記載されています。例えば、退職願と退職届のどちらを提出すべきか、提出時期はいつまでか、書式に指定があるかなど、重要な情報が含まれています。
また、退職予告期間についても就業規則で定められていることが多いです。法律では2週間前までに退職の意思を表示すれば良いとされていますが、多くの企業では1か月前や2か月前までの予告を求めています。この規定を守らないと、円満退職が難しくなったり、場合によっては損害賠償を求められたりする可能性もあります。
さらに、公務員や契約社員、派遣社員などの場合は、一般的な正社員とは異なる手続きが必要な場合があります。就業規則や雇用契約書を確認し、自分の雇用形態に応じた適切な手続きを理解することが大切です。
就業規則が手元にない場合は、人事部や総務部に問い合わせて確認しましょう。退職手続きに関する不明点がある場合は、遠慮せずに質問することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
退職願と退職届の書き方の違い
退職願と退職届は、その性質の違いから文面や書き方にも違いがあります。正しい書き方を理解して、適切な書類を作成しましょう。
退職願の文例
退職願は「お願い」の文書であるため、謙譲語を使った丁寧な表現で作成します。以下に標準的な退職願の文例を示します。
退職願
私事、この度は一身上の都合により、来る令和○年○月○日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
○○部○○課
氏名 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○ 様退職願の特徴的な表現は「退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます」という部分です。これは、退職を「お願いする」という姿勢を明確に示しています。
また、退職理由については「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。具体的な理由を記載する必要はなく、むしろ個人的な事情として処理することで、円滑な手続きが期待できます。
日付については、退職希望日を記載します。ただし、これは希望であり、会社との話し合いによって調整される可能性があることを理解しておきましょう。
退職届の文例
退職届は確定事項を「届け出る」文書であるため、断定的な表現を使います。以下に標準的な退職届の文例を示します。
退職届
私事、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
○○部○○課
氏名 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○ 様退職届の特徴は「退職いたします」という断定的な表現です。これは、退職が確定していることを明確に示しています。
また、退職日については希望日ではなく、確定した日付を記載します。この日付は、事前に会社との話し合いで決定されたものである必要があります。
退職届も退職理由は「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。これにより、個人的な判断で退職することを明確にし、会社側の責任を問わない姿勢を示すことができます。
書き方のマナー
退職願・退職届を作成する際は、以下のマナーを守ることが重要です。
用紙について
- B5またはA4サイズの白い便箋を使用
- 罫線の入った便箋でも、白無地でも構わない
- 質の良い用紙を選び、しわや汚れがないものを使用
文字について
- 縦書きが基本(横書きでも可能だが、縦書きがより正式)
- 黒いボールペンまたは万年筆で記入
- 鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンは使用しない
- 修正液や修正テープは使用せず、間違えた場合は新しい用紙で書き直す
封筒について
- 白い封筒を使用(茶封筒は避ける)
- 封筒の表面中央に「退職願」または「退職届」と記入
- 裏面左下に所属部署と氏名を記入
- のりでしっかりと封をし、封字(〆)を記入
提出について
- 直属の上司に手渡しで提出するのが基本
- 郵送やメールでの提出は原則として避ける
- 提出時は封筒から取り出さず、封筒ごと提出する
これらのマナーを守ることで、誠意ある退職手続きを進めることができ、円満退職につながります。
退職願・退職届を提出するときの注意点
退職願や退職届を提出する際は、タイミングや方法について十分に注意する必要があります。適切な手続きを踏むことで、トラブルを避け、円満に退職することができます。
提出タイミングは退職希望日の1~2か月前が目安
退職願・退職届の提出時期は、円満退職のために非常に重要な要素です。法的には2週間前までに意思表示すれば退職できますが、実際の職場では1~2か月前の提出が望ましいとされています。
1~2か月前の提出が推奨される理由は複数あります。まず、業務の引き継ぎに十分な時間を確保できることです。特に、専門的な業務や重要なプロジェクトに関わっている場合、後任者への引き継ぎには相当な時間が必要です。適切な引き継ぎを行うことで、会社に迷惑をかけることなく、自分自身も安心して退職することができます。
また、後任者の採用や配置転換にも時間が必要です。会社側が新しい人材を採用する場合、求人募集から採用決定まで1か月以上かかることも珍しくありません。社内での配置転換を行う場合も、適切な人材の選定や業務調整に時間を要します。
さらに、有給休暇の消化を考慮することも重要です。残っている有給休暇を退職前に使い切りたい場合、その期間も含めて退職スケジュールを計画する必要があります。
ただし、会社の就業規則で退職予告期間が定められている場合は、その規定に従う必要があります。3か月前の予告を求める企業もあるため、事前に確認しておきましょう。
上司に口頭で伝えてから提出するのが基本
退職願や退職届を提出する前に、まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝えることが重要です。これは、ビジネスマナーとしても、円満退職を目指す上でも欠かせないステップです。
口頭での報告を先に行う理由は、上司に対する敬意と配慮を示すためです。突然書面だけで退職の意思を伝えると、上司は驚き、場合によっては不快に感じることもあります。まず口頭で相談することで、「相談したい」「話し合いたい」という姿勢を示すことができます。
口頭での報告の際は、以下の点に注意しましょう。
話す環境
- プライベートな空間で話す(会議室などを予約)
- 他の同僚に聞かれない環境を選ぶ
- 上司の時間に余裕があるタイミングを選ぶ
話す内容
- 退職を考えている理由を簡潔に説明
- 希望する退職時期を伝える
- 引き継ぎについて前向きな姿勢を示す
- 今後の手続きについて相談したい旨を伝える
口頭での報告後、上司から書面での提出を求められた場合に、退職願または退職届を提出します。この流れを踏むことで、上司との関係を良好に保ちながら退職手続きを進めることができます。
感情的な理由は書かず、シンプルに「一身上の都合」でまとめる
退職願・退職届を作成する際、退職理由の記載には特に注意が必要です。どんなに退職に至った背景が複雑であっても、書面には「一身上の都合により」と記載することが一般的です。
「一身上の都合」と記載する理由は複数あります。まず、個人的な判断で退職することを明確にし、会社側に責任がないことを示すことができます。これにより、退職後のトラブルを避けることができます。
また、具体的な退職理由を記載すると、かえって問題が複雑になる可能性があります。例えば、「人間関係の問題により」「待遇に不満があるため」などと記載すると、会社側がそれらの問題を解決しようとして、退職時期が遅れたり、余計な議論が発生したりする可能性があります。
さらに、退職願・退職届は正式な文書として会社に保管されます。将来的に何らかの理由でこの文書が参照された場合、感情的な表現や具体的な不満が記載されていると、自分自身の評判に悪影響を与える可能性もあります。
ただし、法律で定められた正当な理由がある場合(セクハラ、パワハラ、労働条件の違反など)は、適切な方法で問題を提起することも重要です。この場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
一般的な転職の場合は、面接などで詳しい退職理由を説明する機会があります。書面では「一身上の都合」として簡潔にまとめ、必要に応じて口頭で補足説明を行うのが適切です。
ケース別の使い分け
退職願・退職届の使い分けは、雇用形態や会社の方針によって異なる場合があります。自分の状況に応じた適切な対応を理解しておきましょう。
公務員や契約社員の場合
公務員の場合、一般企業とは異なる手続きが必要になることがあります。公務員の退職は、任命権者に対する「退職願」の提出が基本となりますが、承認を受けるまでは退職できません。また、公務員には様々な種類があり(国家公務員、地方公務員、教職員など)、それぞれに応じた手続きが定められています。
国家公務員の場合、人事院規則や各府省の規程に従った手続きが必要です。地方公務員の場合は、各自治体の条例や規則に基づいて手続きを行います。公務員の場合は、一般企業のように2週間前の通知で退職することはできず、承認を受けるまでは在職し続ける必要があります。
契約社員の場合も、雇用契約の内容によって手続きが異なります。有期雇用契約の場合、原則として契約期間満了まで勤務する必要がありますが、やむを得ない事由がある場合は中途退職が可能です。無期雇用契約の契約社員の場合は、正社員と同様の手続きになることが多いです。
派遣社員の場合は、派遣元企業との雇用契約に基づいて手続きを行います。派遣先企業ではなく、派遣元企業に対して退職の意思を表示する必要があります。
いずれの場合も、自分の雇用形態に応じた就業規則や契約内容を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。
会社独自のフォーマットがある場合
多くの企業では、退職願・退職届について独自のフォーマットや手続きを定めています。このような場合は、会社の指示に従って手続きを進めることが最も適切です。
独自のフォーマットがある理由は、会社の人事管理システムに合わせるためや、必要な情報を漏れなく収集するためです。例えば、退職後の連絡先、社宅や社用車の返却、各種手続きのチェックリストなどが含まれている場合があります。
また、電子申請システムを導入している企業では、紙の書類ではなく、システム上での手続きを求められる場合もあります。この場合は、システムの操作方法や承認フローについて、人事部に確認しておくことが大切です。
独自のフォーマットがある場合の注意点として、必要な情報をすべて正確に記入することが重要です。記入漏れがあると、手続きが遅れたり、再提出を求められたりする可能性があります。不明な点がある場合は、遠慮せずに人事部や総務部に質問しましょう。
また、会社によっては退職願・退職届以外にも、退職に関する様々な書類の提出を求められる場合があります。例えば、業務引き継ぎ書、備品返却書、退職後の連絡先届出書などです。これらの書類についても、会社の指示に従って適切に作成・提出することが大切です。
円満退職を目指すなら、まずは退職願を提出して相談
円満退職を最優先に考える場合は、いきなり退職届を提出するのではなく、まず退職願を提出して会社と相談することをお勧めします。この方法により、以下のようなメリットが期待できます。
関係性の維持
退職願による相談から始めることで、会社や上司に対して敬意を示すことができます。これにより、退職後も良好な人間関係を維持しやすくなります。転職先での業務で前職の関係者と関わる機会がある場合や、将来的に何らかの協力が必要になった場合に、良好な関係性が役立ちます。
調整の機会
退職願から始めることで、退職時期や引き継ぎ方法について十分に話し合う機会を作ることができます。会社の繁忙期を避けた退職時期の調整や、重要なプロジェクトの区切りに合わせたスケジュール調整など、双方にとって最適な解決策を見つけることが可能です。
引き継ぎの充実
相談ベースで進めることで、業務の引き継ぎについてもより綿密に計画することができます。後任者の選定、引き継ぎ資料の作成、実務指導の期間など、すべてについて十分な時間を確保できます。
トラブルの回避
突然の退職届提出は、会社側に混乱を招く可能性があります。特に、重要な役職についている場合や、専門性の高い業務を担当している場合は、計画的な退職手続きが重要です。相談から始めることで、予期せぬトラブルを回避できます。
ただし、退職願を提出する際は、自分の意思が確定していることを前提とすることが重要です。単なる相談レベルで退職願を提出すると、かえって混乱を招く可能性があります。退職の意思は固まっているが、具体的な条件について相談したいという姿勢で臨むことが大切です。
まとめ
退職届と退職願の違いについて、詳しく解説してきました。重要なポイントを改めて整理すると、退職願は「お願い」の文書であり、退職について会社と相談したい段階で提出します。一方、退職届は「確定の意思表示」であり、退職が決まった後に提出する正式な文書です。
一般的な退職手続きの流れは、「退職願の提出 → 会社との話し合い・承認 → 退職届の提出」となります。この流れに従うことで、円満退職を実現しやすくなります。ただし、企業によって独自の手続きやフォーマットがある場合は、会社の指示に従うことが最も重要です。
退職手続きを進める際は、就業規則の確認、適切なタイミングでの提出、上司への事前相談など、様々な点に注意する必要があります。また、書類の作成では正しいマナーを守り、退職理由は「一身上の都合」として簡潔にまとめることが一般的です。
退職は人生の重要な転機の一つです。適切な手続きを踏むことで、前職との良好な関係を保ちながら、新しいキャリアに向かって歩み出すことができます。本記事の内容を参考に、自分の状況に応じた最適な退職手続きを進めてください。トラブルのない円満な退職が、新たなスタートをより良いものにしてくれるはずです。